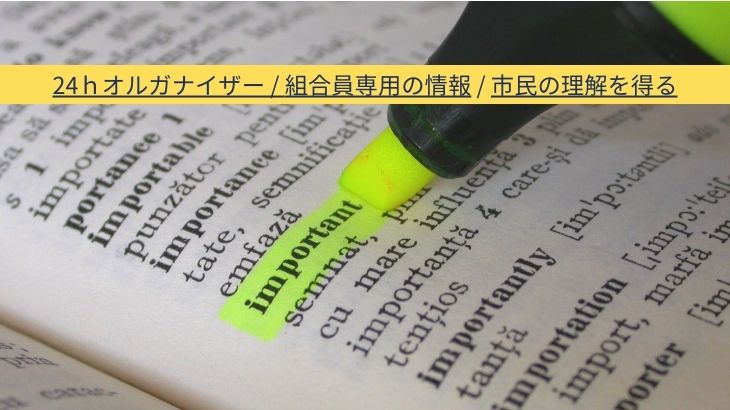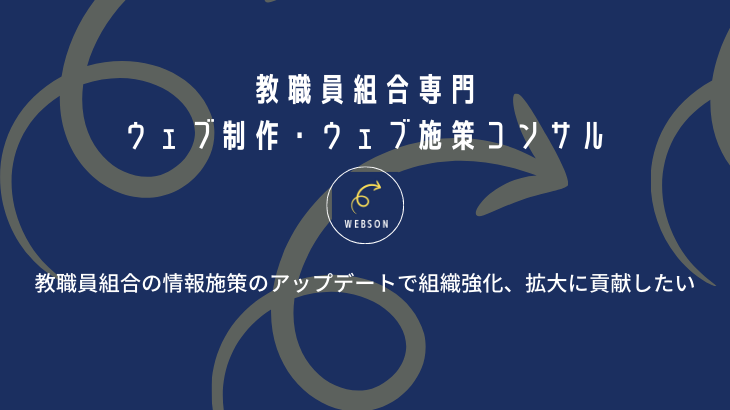ウェブマーケティングの世界において、マイクロコミットメントという言葉があります。
個人の小さな行動や責任を意味する言葉です。
すなわち、消費者がブランドや製品に対して微小ながら積極的な行動を起こすことです。例えば、ニュースレターの購読やアンケートへの回答などです。
これらの小さな行動は、消費者とブランドとの関係を強化し、信頼を築く基礎となります。そして、このマイクロコミットメントが、製品やサービスの購入の可能性を高めてくれるという考え方です。
このマイクロコミットメントは、労働組合運動においても、非常に有用だと考えられ、組合運動活性化のポイントになってきます。
組合員さんの「できるところで協力したい」をかなえるのがマイクロコミットメント
私が長く役員を続けて来て感じていることがあります。
それは、
できるところで執行部に協力したい
と思っている組合員さんがけっこうたくさんいるということです。
「いつもごこくろうさま」と具体的に声をかけてくれる人もいれば、間接的に「ありがたいな」と言ってくれているという話を聞いたりしました。
また、積極的にそう思ってはいなくても、簡単にできることがあるのなら、やってみようかという人も潜在的にいるのではないかと思っています。
日々の生活と仕事で精一杯の中で、組合運動という行動を起こし、責任を果たせていないな、できることがあれば協力したいという思いを持っているわけです。
この思いにこたえるのが、マイクロコミットメントという考え方を取り入れた組合運動なのです。
労働運動とマイクロコミットメントの親和性高い?!
そもそも、労働組合運動は「組合員による、組合員のための、組合員の運動」です。
執行部は組合員のみなさんの声を受けて、信託を受けて運動をすすめているわけです。その仕組として、月ごとの分会代表者会議や分会会議や動員といった仕組みがあります。
しかし、現場の多忙化がすすむ中、組合員さんの多くは、なかなかこれらの「行動」に参加することができずにいるという現状です。
この現状を打開する方法の1つとして、マイクロコミットメントが有用だと思いませか?
1クリックレベルの「行動」であれば、ちょっとやっとこうか・・・という組合員さんもいるのではないかなと思うのです。
そして、次のようなサイクルを作ります。
組合員のマイクロコミットメント → 執行部に届く → 届いたことを知らせる →組合運動を支えていることを知らせる
自分の行動が「ああ、届いているんだな」と感じてもらうことで、さらにマイクロコミットメントを促進します。
具体的にはどうするか
執行部への応援
交渉の報告記事などの最後に「応援する」ボタンを設置。ボタンをタップした後、応援へのお礼メッセージへ遷移する仕組み。これだけでもよいのですが、このタップをカウントできる仕組みを入れておけば、機関会議などにおいてでも、具体的な数字でお礼と報告をすることができます。
簡単なフォームをつくれば、LNE公式やHPの導入などはしなくても、この仕組みを構築できます。
興味あるな?→クリック
ライン公式アカウントなどのメッセージで記事の概要を伝え、「詳細を確認」ボタンを設置。ブログ記事へ遷移します。ニュースにQRコードを貼っておくのもよいでしょう。
ライン公式アカウント + ブログという形ですが、ブログの記事を次のようなものに置き換えてもOkです。
- ネットのニュース記事
- 上部団体のHPの記事
アンケートで声をとどける
ウェブフォーム(GoogleフォームやMicrosoftFormsなど)を使ってアンケートを作成。ライン公式アカウントやQRコードでアクセスしてもらいます。もちろんオフラインのメディアにQRコードを掲載でもOK。
- これまで紙で行っていた、要求書作成にむけてのアンケートをウェブで行う
- 現場の課題についての考えを聞く
始めるときのポイントとしては、
簡単にできる
- いきなり、10分くらいかかるようなボリュームのあるものは、ハードルが高いです。「マイクロコミットメント」ですから、2〜3分で終わるようなものがよいでしょう。
口コミで広げる
- ことをお願いする。リンクを送信するだけで広げることができるので、執行部からは、知り合いにどんどんリンクをラインなどで送信するとよいでしょう
短いスパン
- 最初はできるだけ短い期間でアンケートを実施、結果の報告のサイクルを作ります。ある程度認知があがってきたら、「交渉にむけて」のアンケートなど具体的な目的をもたせたものをするのもよいでしょう。
アンケートをしたら、何かの活動に繋げなければならないと思うかもしれません。
しかし、この「アンケート」は組合員さんとのコミュニケーションが目的です。組合員さんたちがどんな考えをもっているかを日常的に把握していることが、執行部の動きにとってはとても大事です。ただし、とりっぱなしはよくないので、ごく簡単な報告は必要です。
集計は自動でやってくれるので、出てきた円グラフのスクリーンショットをニュースに掲載したり、ライン公式アカウントやホームページで見てもらえるようにしたりすることで、「ああ、届いているな」と実感してもらえます。
組合員さんの行動→組合の活性化
組合運動というのはそもそもマイクロコミットメントのかたまりだと言えます。
これまでは、動員参加、交渉参加、分会での会議、アンケート、署名などがこの役割を果たしていたと言えます。
動員に参加すれば、学びもあります。交渉や会議に参加すれば学校の枠をこえたつながりができます。
しかし、多忙化がすすむ現在、これまでのこの行動は相対的に「マイクロ」と言えなくなってきています。それは、組合員減少、モチベーションの低下などなどいろいろな要因が重なっていますが、現状として、動員参加、会議参加はなかなか大変な状況である現実。現場における分会会議もなかなか開催できていない状況ではないでしょうか。
「がんばってやらないと!」だけではなかなか太刀打ちできない状況があります。
組合運動は沈滞していきます。
そこで、このマイクロコミットメントの考え方を使って、組合員さんが「小さな参加」ができる仕組みを構築するのです。
そして、その小さな参加が組合を強くし、より生きやすい社会につながるのだということを、地道に見せていくのです。
一人ひとりの組合員さんの参加によって支えられている組合運動。すなわち、組合運動の王道です。