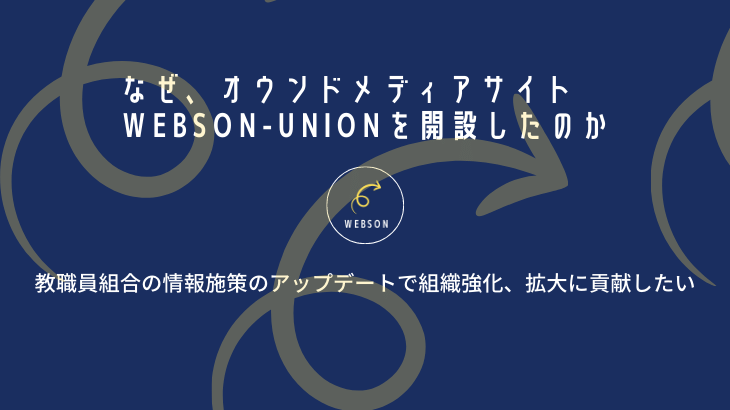組合運動にとって、重要な機能として、
現場の声を教育委員会(文科省)に届ける
ということがありますよね。
すでに、多くの組織で取り組まれていると思いますが、ウェブの技術を使って、効率的に現場の声を集める方法を紹介したいと思います。
最初に確認しておきたいのは、現場の声というのは、聞けば返ってくるというようなものではなく、執行部と現場、現場の組合員同士、現場の教職員間のコミュニケーションの中で、より具体的に、より解像度高く見えてくるものであるということです。そのため、王道はやはり、機関会議や分会訪問などによるオフラインのコミュニケーションであることは言うまでもありません。
ウェブのツールについては、この過程全体の量と質をあげていくものとして、活用することが大切であるということです。
現場の声は不満や不安から
日々現場で働く教職員にとって、「現場の声をください」と言われて、「OK」と言ってとりかかるのは思いのほか簡単ではないです。
- 要求にするのであれば、きちんとまとめないと。
- ちゃんとした理屈で言わないと。
- 自分だけのわがままではないかな
こんな不安を感じる人も多いものです。
何かが改善するときというのは、だいたい、愚痴や不満がきっかけになることが多いわけで、現場の皆さんには遠慮なく、愚痴や不満をぶちまけてもらうことが大事です。それを、交通整理したり。理屈を補完したりして、要求にまとめあげるのが執行部の役割なのだということを、日頃から自組織の文化になるくらい浸透させておきたいものです。
オフラインも含めて、オンラインでも気軽に、忖度なく愚痴や不満を届けてもらうところからスタートです。
いつでもどこでも声をとどけることができる
これまでの組合運動における、声を届けるシステムとしては
- 執行部による分会訪問
- 機関会議
- 電話
などが主なものでした。
これらの特徴は、コミュニケーションの親密度は高い、即時性にかけるというところです。
ウェブのツールはどうでしょうか?
コミュニケーションの親密度はオフラインほど高くはありません。しかし、現場の教職員の都合でいつでも声を届けることができます。また、最近では、インタラクティブ(双方向)の仕組みもいろいろと充実してきていますし、少しの工夫で少しコミュニケーションの親密度も高めることができそうです。
オフラインのとりくみに比べて、行動にうつすハードルもぐんと低くなります。
HPのフォーム
HPを持っていれば、だいたいコンタクトフォームがあります。
シンプルに名前、メールアドレス、内容だけのものでもよいですし、WordPressなどを利用しているのであれば、いくつかのフォームを目的別に設置することなども、比較的簡単にできます。
しかし大事なのは、このフォームへの導線が、「簡単な形」で確保されているということが重要です。
ユーザーが、ちょっと「届けたい」と思ったときに、スマホを出して、さくっと入力、送信できないと、そのメリットはあまり発揮されません。
フォーム作成、管理ツール(Googleフォーム、Formsなど)
HPのフォームと同様の機能を持っています。こちらは、さらに簡単に、フォームを作成できます。
1,2問だけの簡単な質問で、サクッとアンケート作成などに活用できます。月に1回など、定期的にアンケートを作るということも、紙ベースでやるよりは、ハードルが低いです。
フォームの内容についてもいくつかポイントがありますが、これはまた別の機会に。
これもHPと同様、導線を確保することがとても重要です。
もし、定期的にアンケートをするのであれば、定番のチラシにQRコードを貼り付けて配布するなどすれば、回答数の増加にもつながるでしょう。
ライン公式アカウント
ライン公式アカウントは、メッセージ送信数が月に200通をこえると月額5000円が必要で、月に5000通まで送信できるようになりますので、多くの組織において活用しようと思えば月額の固定費用がかかってきます。
活用するのであれば、しっかりと成果につなげ、組合員さんに見えるようにしたいところです。
標準では選択肢を選ぶ程度の簡単なアンケート機能がついています。また、個別にLINEのようにメッセージのやりとりもできます。大きな組織になると対応が大変なので個別チャットはオフにするほうが良い場合もありますが、登録者数が多くなるまでは、この機能も活用できます。
さらに、このライン公式アカウントを拡張するサービス(プロライン、Lステップなど)を導入できれば、活用幅は大きく広がり、充実したフォーム機能ややりとりの自動化などができます。
組合員さんがいろいろな情報にアクセスするための導線という役割が主なものとなります。
効果1 インタラクティブなコミュニケーション→組合員のコミット感
マイクロコミットメントという言葉があります。
人間は少しの行動を起こすことで、その組織へのコミット感を感じるということです。
広告の世界では、簡単に「クリック」してもらうことで、その後の購買行動へつなげるという意図で使われたりしています。
そもそも、組合運動というのは、「だれかが何かをやってくれる」ものではないですよね。でも、近年現場の多忙化が進み、組合員であっても、なかなか組合にかかわる「行動」を起こせない人も増えていると感じませんか?
そんな組合員さんの多くは、
「執行部に任せきりで自分は何もできていないな」
と感じていたりもします。
そこに、「マイクロコミットメント」の考え方を導入して、ウェブの技術で組合員さんが行動できるチャンスを作ることができるのです。オフラインで動員にはなかなか行けないけど、オンラインでちょっとメッセージ送るとか、ちょっとボタンタップするとかなら、数秒で終わるわけです。
そこに組合運動につながる意味を提示できれば、「少しだけど行動できたな」と感じることができるのではないでしょうか?それが、組織へのコミット感にもつながっていきます。
具体的な方法やとりくみはまたの機会にご紹介したいと思います。
効果2 執行部の活動の可視化〜組合員さんに運動が伝わる
これらのとりくみを行うのには、もう一つの意図があります。
それが、執行部の動きの可視化です。
今の組合の組織率が低くなってきていますが、その1つの要因として「組合がやっていることが見えない」ということが見えにくい」ということがあります。
どうやって執行部や組合のとりくみをみせていくのか、ということに腐心している組織も多いのではないかと思います。
このフォームを活用したアンケートやライン公式アカウントの活用においては、組合員さんにとっての利便性や組合運動の王道であるということに加えて、執行部の活動をどう見せていくかという観点を持っておくことが重要です。
現場の課題は、一朝一夕に解決するようなものはそんなに多くはありません。
だからこそ、組合員からボトムアップの情報が生かされ、執行部が動いているということがみえるようにしておくことは、組合の組織維持の観点からも、組合員さんの満足度からもとても重要なポイントです。
現場の声あつめてくれているな。
声が教委に届いているな
そんなことが、一人ひとりの組合員に見える形をつくる。ウェブの技術を活用すれば、そんなことを実現できるのです。
組合員さんのコミット感アップと執行部の動きの可視化が互いに良い影響を与え合う
ウェブを通してつながることで、執行部と組合員の距離感をぐっと縮めることができる。そんな提案です。この記事ではあまり具体的なことに言及していませんが、
● それぞれの組織の状況に応じてとりくむこと
● 最初あまり成果を感じられなくても、継続していくこと
この2つをポイントにして施策を立案するといいと思います。
組合員さんからのコミットによって反応が見えれば、執行部は元気になり、それが組合員さんに伝わることで、さらに組合員さんのコミットが高まります。
よく考えると、これって、組合運動そのものなんですよね。