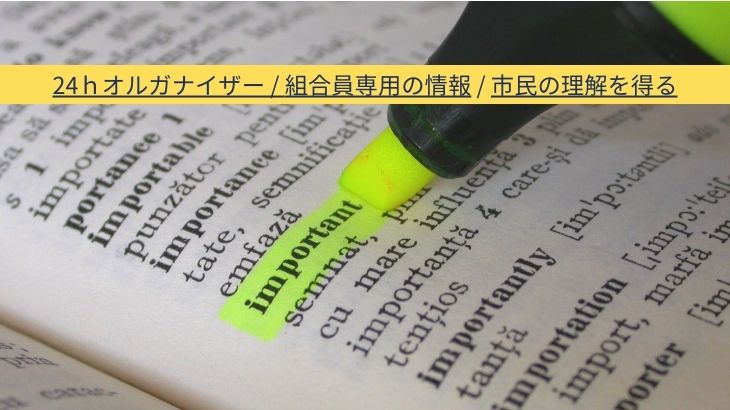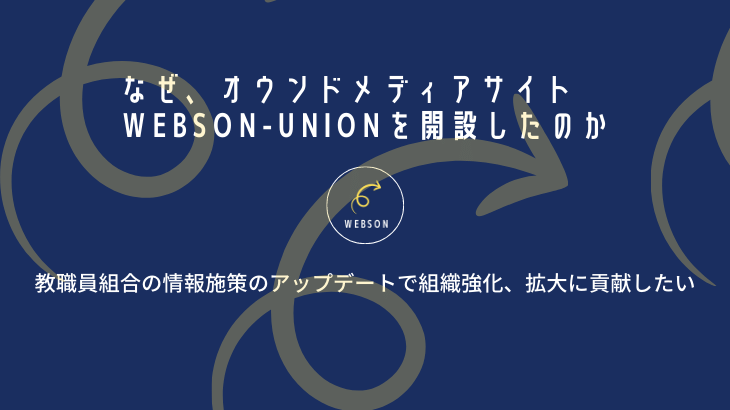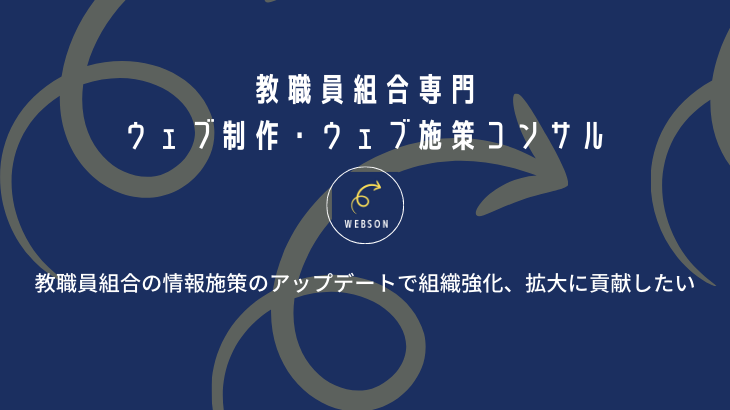ホームページあったらいいのかな?と思いつつも、でも、どうすればいいかはよくわからないし、お金かけるとしても、それがどういうメリットがあるのか今ひとつわからないなあ
そんなふうに感じている役員さんはけっこういるのではないでしょうか?
この記事では、教職員組合がHPを持つことでできることを3つに絞って、解説していきたいと思います。
この記事を書いた人
24hオルガナイザー
店舗のHPは「24h働く営業」と言われていたりします。
同様に教職員組合にとっても、ホームページは24hオルガナイザーになりえるものです。
オープンショップ制の教職員組合にとっては、オルグという行動が欠かせません。ホームページは、このオルグを24hやってくれるということです。
例えば、人事委員会勧告が秋に出ます。この時期に合わせて、1つの記事を用意しておきます。一般的なものよりも、自分の都道府県での具体的な運動についても、きちんと記載しておくことが大事なポイントです。
従来の組合運動においても、人事委員会勧告の時期には、機関会議において分会や単組の代表者に解説し、それを組合員に周知、ペーパーでの情報を発出、組合員に周知、さらに情報を得た組合員はその情報を職場の同僚に伝える(これがオルグですね)という流れがあったと思います。
この記事は次のように活用することができます。
- 単組や分会の代表者が聞いた話の覚書のように使用
- 組合員が読むことで理解が深まる
- 未組合員が読むことで組合の運動が伝わる
- 組合員が未組合員に記事リンクを渡すことができる
記事を読むのに時間は関係ありません。
読みたい人が読みたいときに読むことができます。
これって、記事を読んでいる未組合員をオルグしているというのと同じような(同じではない)効果が生まれているといえませんか?
そして、ホームページに力がついてくると、「人事院勧告」などで検索している人の検索結果に表示されるようになったりもします。
もちろん最後のひと押しは隣の同僚や先輩からの声かけが必要ですが、場合によってはホームページに設置された問い合わせフォームが力を発揮することもあります。
組合員専用の情報
一般的な会員サイトでは、以下のような流れをとるものが多いです。
メールアドレス登録 → ログイン → 会員専用のエリアへアクセス
でも、これはけっこうハードルが高いんですよね。
このサイトでも使用しているWordPressでは、記事にパスワードを掛けることができます。また、あるページにパスワードをかけて、そこからしかたどり着くことができないようなページを作っておくということもできます。
パスワードがわかれば誰でも入れますので、完璧な組合員専用ではないですが、まずは、このような仕組みから始めるといいと思います。次のような効果があります
- 組合員満足度向上
- 未組合員の興味をひく
組合費を収めていただいている組合員さんが、入っててよかったと思えるようなしくみをできるだけ用意して、それが見えるようにしていくことは、組合員さんの満足度向上に効いてきます。
市民の理解を得る
組合の運動にとって市民の理解は大事ですよね。
「働き方改革」の推進についても、学校のユーザーである保護者をはじめ、市民のみなさんが、学校の現状を理解するということが大事になってきます。
これまで組合運動では、PTAと一緒に取り組みをしたり、市民団体と取り組みをしたりということをやってきたと思います。しかしながら、組合員の現象、現場の多忙化によって、このような取り組みの縮小を余儀なくされているところもあるのではないでしょうか?
ホームページを使って、教職員組合がやっていることを発信することで、市民の理解につなげていくことができます。
教育研究集会を開催しているところでは、市民の参加もOKとしているところも多いかと思いますが、そのような取り組みの宣伝にもホームページ(+SNSの)は最適です。
組合運動で必要なことはいつも同じ
結局は、今までやっていた運動は変わらないということではないかなと思うわけです。
やりたいことややるべきことは変わらない、でも、その方法は時代に合わせて進化させていくことが必要です。
これまで、紙の機関紙の印刷については、プロに依頼していたところもあるかもしれません。プロが作ったものの質は格段に高いです。この質の高い機関紙は、組合員にとって、自分の所属する組合がしっかりした組織であるというステータスにもなり得ていたと思います。
しかしながら、現場の多忙化、紙の情報の氾濫、紙以外の媒体の増加によって、組合員にとってのその価値は相対的にさがってきています。
そこでWEBを活用しようとホームページを自前で作って運用しているところも多いと思います。
ホームページの制作・運用も印刷と同様、プロの視点が加わると様々な効果を発揮します。
「新しいことをしなければならない」のではなく、
「これまでもやってきて、これからもやっていく組合運動をより効果的に行う」
ための1つのツールとしてWEBの技術を活用するという観点が大事ということです。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事では、以下の3つの場面で教職員組合のホームページが意味を持つことをお伝えしてきました。
教職員組合にとってHPが重要な3つの場面
24hオルガナイザー
組合員専用の情報
市民の理解を得る
もちろん他にもホームページの活用できる場面は多くあります。
ご興味湧きましたら、フォームよりお問い合わせください!
オンラインでのご相談については、以下のボタンから日時をご指定いただいても大丈夫です。