はじめまして。
現在、個人事業主としてホームページ制作やウェブ施策のコンサルティングをしている、孫弘樹(そんほんす)と申します。
2023年3月31日に教員を退職するまで、単組執行委員長を務めておりました。
そんな私が教職員組合の情報施策のアップデートに貢献したいと思ってはじめたのが、WEBSON-UNIONの事業です。
あなたの組合でも、もしかしたらすでに、SNSを運用していたり、ホームページを持っていたりするかもしれません。次のようなことで悩んだことはありませんか?

ホームページうまく作れないなあ

運用しているけど役に立っているのだろうか

SNSなかなか広がらないなあ、
また、まだHPもなく、SNS運用もしていないのであれば、こんなことを考えたことはありませんでしょうか?

現場が忙しくなり過ぎで、組合員さんが組合活動できづらい
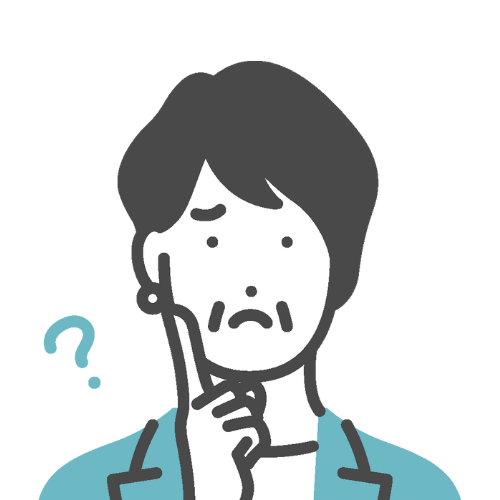
組織率が年々下がっている

執行部のとりくみがしっかり伝わればわかってもらえるのに・・・
このような悩みをお持ちでしたら、一度、このページにお付き合いください。
この記事を読んでいただくと
- 私UNION-WEBSON代表孫弘樹(そんほんす)がなぜ、何を、この事業をやりたいのかということが少し見える
- WEB技術と組合運動をかけ合わせて、組合の状況を改善していくきっかけがみつかる
ぜひ、最後までお付き合いください。
なぜ、この事業(教組へのウェブ提案)をはじめようと思ったのか
組合運動はよりよい社会をめざすもの

教員を辞めてまで、組合の施策に関わろうとする理由の1つは、私が組合運動の中で得た気づきです。
組合運動で表現しているのは「自分がどんな社会に暮らしたいか」ということ
1人ひとりの人権を大切にできる、多様性が前提の、誰もが生きやすい社会にしていきたいという思いがあります。
X(旧Twitter)では、教職員の「愚痴」(愚痴は宝ですが、そこでは宝になれる確率はとても低い)が日々流れてきます。
それをみるたびに、「みんな組合に入ればいいのに」と思ってながめています。
なかなか広がらない組合→WEB技術を学ぶ中での気づき〜使える!
私が組合運動を担っているとき、多くの組織がそうであるように、やはり組織率や組合員数は減少の一途を辿っていました。
しかしながら、私の自治体の教職員数に対しての組合員の割合は、おおむね現状維持でした。
大きく増えることはなかったのですが、私の単組の周辺単組の状況を考えれば、健闘したのではないかと思っています。
ふりかえってみれば、分会訪問をしたり、機関会議の方法を改善したり、オフラインのとりくみをいろいろと考えたのと同時に、オンラインもうまく活用したいと思って、チャレンジしたことも要因ではないかと思っています。
私たちの生活に入り込んでいるWEB技術
日常生活でのいろいろな人とのお付き合いを考えると、そこに、WEBの技術がたくさん入り込んでいることにも気づきました。そう、少し古くはWEB検索、そして、LINE、SNSです。
これを考え合わせると、組合運動にもこのWEB技術を取り入れることもできるのではないかと思ったわけです。
もう10年くらい前のエピソードを紹介します。
当時専従をしていた私は、ブログを開設しました。
すると、教委とのコミュニケーションでこまっている休職中の教職員(未組合員)が、ウェブの検索からたどり着いてくれました。
教委の対応を改善、その方が現職を継続することができました。その後の休職者への脅威の対応の改善にもつながりました。
その後、オフラインの取り組みの改善とかけあわせながら、ワードプレス(HP作成システム、CMSと言います)でHPを作成、FBページ開設、ライン公式アカウント(組合員専用)開設、Googleフォーム活用などすすめました。
いろいろ気づきがありました。
- 結局ウェブでやっているのは、組合全盛のときにオフラインでやっていたコミュニケーション。
- いろいろな手続をWEBにすることで、組合員さんが組合の利用をしやすくなった
- 定期的なアンケートなどで、いろいろな現場の声をあつめやすくなった
教職員組合の情報施策に貢献
私自身は、自分自身の自己実現のために、教職員を退職しましたが、「組合が大事だ」ということが、おおむね社会で共有されてほしいという思いは今も持っています。
数年ほどホームページ制作などWEB周りのことを学び深め、業務でも経験を積んで来て、これらの技術を教職員組合へおかえししたいと思いました。
伴走型でやっていきたい。あなたの組合の状況を聞かせてください。
HPは作ってハイ終わり、というわけではなく、作ってからが本番です。
- HPを組合運動にどうつなげるのか
- いかに効率的に情報施策をまわしていくのか。
私が単組執行委員長時代にやってきたことをそのままやることが良いわけではないはずです。
コミュニケーションをとりながら、私だからこそ持っている組合運動×WEBの視点を提供したいと思っています。
どんなことができるのか
HP制作
だれになにをとどけるためのHPなのか。まんぜんと公開しているだけではもったいないのがホームページ。
最初のターゲットはどこ?やはり組合員?いや、組織拡大だから現場教職員みんなに!いずれは社会対話のツールに!
組合運動と同様、息の長いとりくみです。今の状況に合わせて、ロードマップを共有しつつ、すすめていきます。
ライン公式アカウント開設支援
LINE公式アカウントの強みは、驚異的な開封率です。要するに、情報が届きやすいということです。
これを活用しない手はありません。
執行部での運用体制をどう整えるのか、組合員さんが「いいな」と思えるような運用を考えていきましょう。
HP運用支援
HPは継続的に育てていくものであるという認識のもと、運用をしていきます。
今ではブログ型のものがほとんどですので、記事を継続的に作っていくことが大事です。継続することで
- 記事を毎年活用できる
- 新しい執行部メンバーが、これらの記事を読むことで、組合のことがわかる
- 組合員さんがオルグツールとして使える
など、活用法は様々です。
継続するための計画立案、WEBで読みやすい記事の書き方、ポイントなどについても、みなさんにお伝えいたします。
あなたの組合のことはあなたが一番良くわかっている。だから中の人でできるように支援します
最終的には、私が関わらない形をめざします。
「あ、そんさんもういなくて大丈夫」といっていただけるようにしたいと思っています。
組合運動とWEB技術の親和性について発信
単組委員長時代に実践したこと、今持っている発想など、次のメディアで発信しています
よかったらときどきのぞいてください。
一度、ご相談ください。ちょっとお話だけでもOKです。
組合運動の王道はオフラインのつながりの中での、オルグ活動です。しかしながら、現場の多忙化、組合組織率の低下の中で、とてもむずかしい状況にあります。
一方、WEB技術の進化はとても早いです。中には、「そんなバーチャルなものは組合運動にはなじまない」という考えの方もいるかも知れません。
私からの提案は次です
これまでの組合運動をさらに補完するものとして、WEBを活用する
WEBの技術が進化し、その恩恵は組合員さん、現場教職員の生活に欠かせないものとなっています。だからこそ、組合運動にもこの技術を活用することで、多くの人に思いが届くという考えです。
まずは、話だけでも聞こうかというのでも大丈夫です。
ご連絡ください。
早速、ミーティングの予約を入れていただくこともできます。
LINE公式アカウントに登録していただき、そちらからメッセージを送っていただいてもOKです。


