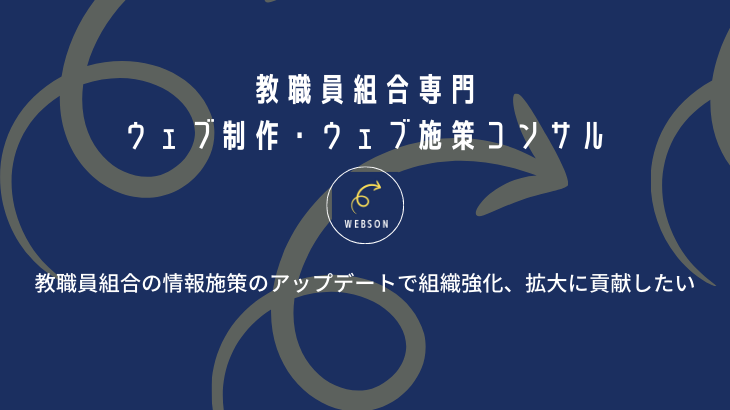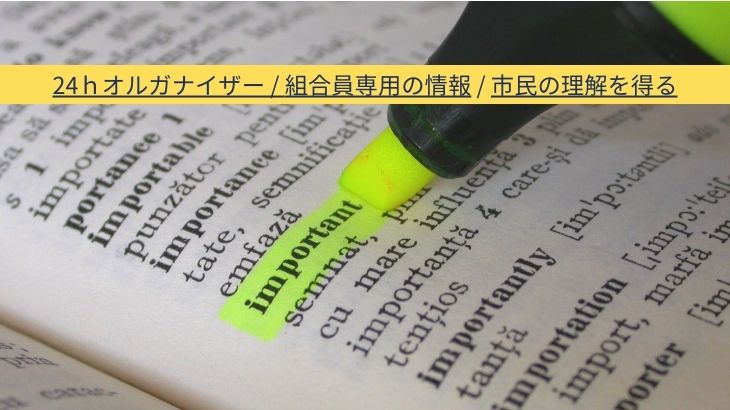この記事では、組合運動で大事にしている組織拡大のとりくみについて、考えます。
オープンショップの組合においては、組織拡大のとりくみがとても大切ですよね。
一人ひとりの組合員が隣の人に組合の意義を伝え、組合の加入をすすめるという意識をいかに持ってもらうかというところに執行部のみなさんは腐心されているところだと思います。
実はこれまで組合運動とWEB技術は親和性がとても高く、少し理解を深めることで、これまでの組合運動をさらに効果的にすすめるツールになり得るということを、この記事でご理解いただければと思います。
これまでの組合運動のとりくみのありかた
情報の伝達手段 機関紙 / 会議 / 電話
これまで組合運動では、機関紙の発行、各種機関会議、そして電話が主な情報の伝達手段でした。特に機関紙は制作と配布に時間とコストがかかる一方で、信頼性がありました。機関会議に参加した分会代表者(分会責任者)が各分会において、分会会議を開催し、すべての組合員に情報が伝わるという仕組みです。
即時性:夜遅くまで執行部が集まってニュースを発送する
緊急な情報、例えば給与確定の情報などです。
給与交渉では交渉がずれこみ、最終回答が夜になることなども多く、その情報が確定次第、機関紙を作成します。そのために、時には執行部が夜遅くまで集まって発送していた(いる)ところもあるのではないでしょうか。
組合員が組合員に伝える・組織拡大
- オフラインでのネットワーキング
- 会議
- 口コミ
オフラインでの会議や集まりが主な場で、組合員から組合員への情報共有や新規加入の勧誘が行われてきました。口コミが特に重要で、組合員同士のリアルなつながりが大きな力を持っています。
これらの取り組みの中で、組合運動は以下のようなことを組合員、現場に提供してきました。
- 情報
- 双方向のコミュニケーション
- 困ったときの相談窓口
これらの組合運動がWEBの技術を使うことで、更に効果的に行えるとすれば、やってみないという選択肢はないのではないでしょうか?
組合員は組合のことを大切だと思っている→できるところで貢献したいという思いを実現する仕組み
執行部を続けてきて年々強く感じるようになったことです。
組合員一人ひとりが、自分が所属する組合を非常に大切に思っています。そのため、それぞれができる範囲で貢献したいと考えています。
それが、年々多忙化する実態の中で、できることが減っていってしまっていました。
また、分会での伝達機能、すなわち、分会会議の開催もなかなかできない分会も増えてきました。新しく組合に入った組合員は、これまでの運動のあり方がわからず、何をどうすればいいのかわからないという状態もありました。
そして、多忙化する現場においても、なにかできることがあるのではないか!という思いで、WEBの技術の活用にとりくみはじめました。
ペーパーでの情報発信 → WEBでの情報発信媒体を持つ
- HPでの情報掲示
- WEBの即時性
- LINE公式アカウントでの速報
まず、「情報伝達」の仕組みです。
多くの新聞にWEB版があるように、これまで紙の機関紙が担ってきた「情報伝達」をWEBで行うことができます。もちろん、社会においても、学校現場においても、紙の情報は必要なので、互いをかけあわせて、さらに効果を発揮させていくことができます。
WEBを活用するメリット
ペーパーでは表現できない程の即時性。例えば、組合員専用のセキュアなウェブページで重要な情報を即座にアップデート可能です。
双方向性。ライン公式アカウントやフォームの活用で、組合員は手軽に、時間を気にせず、執行部へのメッセージを伝えることができます。発信した記事の最後にフォームを付けて、執行部への応援メッセージを選択できるようにすると、少しほっこりしました。
また、ブログ形式で作成した記事は、ウェブ上に残り続けます。例えば、給与確定情報などであれば、毎年の大まかなとりくみと、組合の果たす役割などを解説する記事+年度ごとの情報という形にしておけば、年度ごとの情報を変更するだけで、毎年使うことができます。
あとはURLを拡散すれば、多くの組合員がそこにアクセスすることができるのです。
このあたりについては次の記事に詳しく書いています。
課題
学習コストが一定かかる。HPの作成は手軽にできるようになっているとはいえ、専門的な仕事です。一定の質を求めるのであれば、そんなに簡単ではありません。
記事の更新程度であれば、一度学んで何度か体験すれば、ワードで文書を作るくらいの間隔でできるようにはなりますし、ネットを通しての活動なので、場所を選ばずとりくむこともできます。
また、開設しただけでは、まだ誰にも見てもらえませんので、オフラインとの掛け合わせが重要です。まずはターゲットを組合員にすることで、オフラインの施策でQRコードを広めるなどして、組合員のアクセスを促す施策が必要です。
情報の双方向性
WEBを使うと、双方向性をうまく活用することで、簡単にコミュニケーションを深めることもできます。
こまったときの相談窓口
組合の重要な機能の一つとして、相談機能があります。
これまでは電話と分会の代表者やとなりの組合員が主な窓口となっていましたよね。
これも多忙化の中で、なかなか機能しづらい現実がありました。また、「組合に相談すればなんとかなる」という感覚も持てず、とにかく日々の業務にとりくむ毎日という組合員、現場教職員の姿がありました。
- オンライン相談窓口
- フォームやチャットで相談受付はいつでも
そんなこと対応できない!という声が聞こえてきそうですが、以下のようなスタイルをしっかりとお知らせすることもセットで大切です。
- フォームへの送信はいつでもOK
- フォームをうけて、改めて(2,3日中、自分の組織状況に応じて設定)連絡をします
- 電話、または、オフラインで面会しての相談をうける。
- 特に専従をおいていないところは、そのことも丁寧に伝えて、共助の組織であるということを確認しておく
そんなにすぐに対応してもらえないじゃないかというふうに見えるかもしれませんが、相談者にとって、ファーストコンタクトをいつでもできる、その後は連絡を待つ、その期間がある程度約束されているということは、安心につながります。
「電話をかけてもなかなか繋がらない」という状況よりは断然よいのではないでしょうか。
まとめ
- HP+ライン公式アカウントの可能性
WEBサイトとライン公式アカウントを組み合わせることで、既存のオフライン活動と並行して効率的な情報発信が可能です。最初は多くの人がすぐに訪れないかもしれませんが、徐々に認知度が上がり、効果を実感できるでしょう。
このように、WEB技術を上手く活用することで、これまでの組合運動をより効率的、かつ効果的に行うことが可能です。オンラインとオフラインの両方の利点を活用し、より多くの人に組合活動を広めていきましょう。